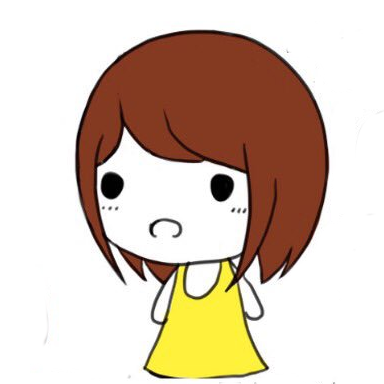
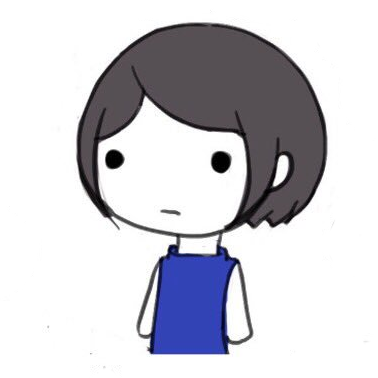
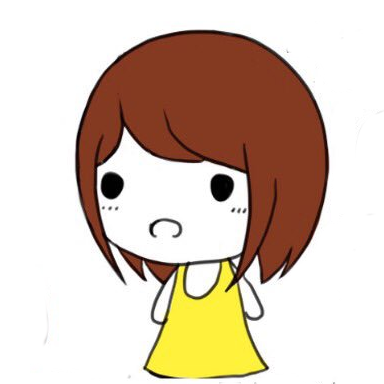
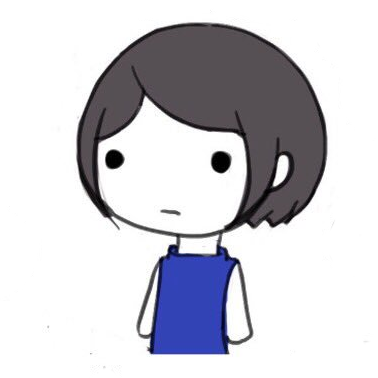
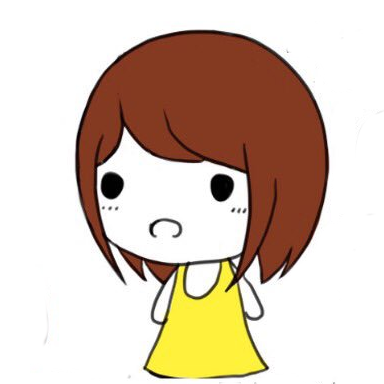
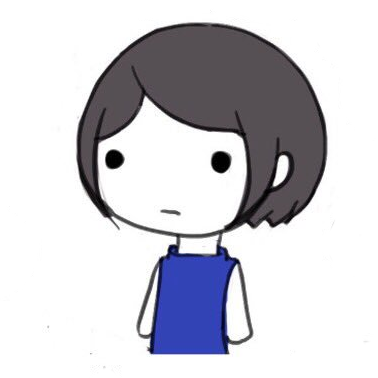
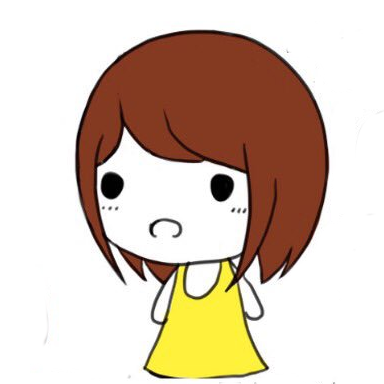
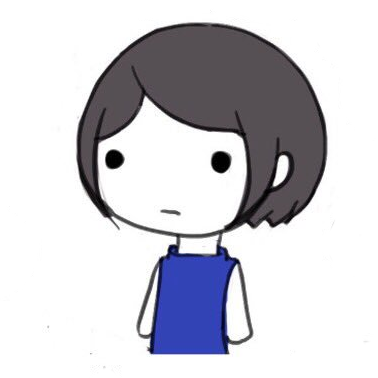
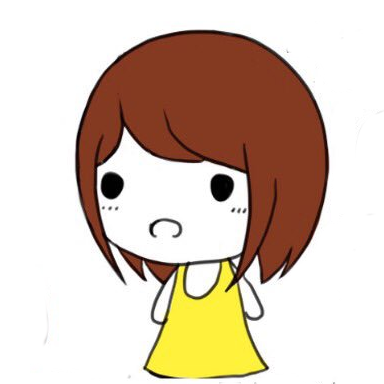
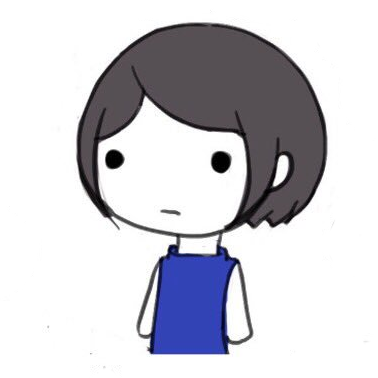
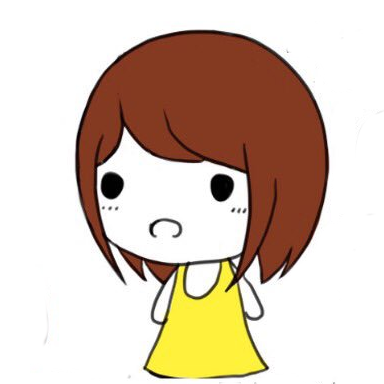
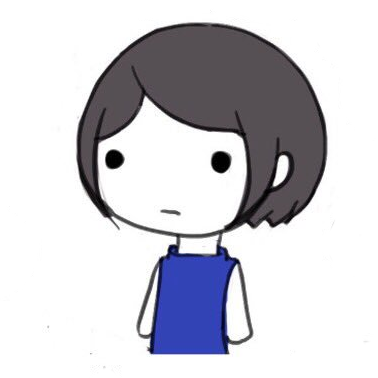
『現代哲学入門』(西脇与作著、慶應義塾大学出版会)を読む。2009 年初版第 4 刷発行なので決して真新しい本ではないけど(実際、カバーを紛失している)。
「はじめに」(p. 1)の所に少し気になる記述があった。
無神論者が「神は死んだ」と叫んでも誰も驚かないが、神父が同じ台詞を言ったなら、誰もが不安を覚えるだろう。
早い話が、前者もある意味驚くに値する。「神は死んだ」ということは、死ぬ前には神はいたからである。ニーチェは「我々(近代人)が神を殺したのだ」と言ったのに対して、デモクリトスとか、マルクスとか、サルトルとか、ドーキンスといった所謂無神論者に言わせれば、神は「もともといないし、これからもいない」のである。
そりゃ五百円チョコは食べると「なくなる」(無くなる?失くなる?)が。「失神論」というと変な意味に捉えられ兼ねないな。
こういう時私は放送大学の講義やテキストに言及すべきかは迷うが、某講義ではテキストにまんま「ニーチェは無神論者ではない」という見出しがあって、「神は死んだ」というフレーズについては「ホッブズが王権神授説を無視して社会契約論を提唱した頃から、世界を説明するのに『神』という概念が次第に必要なくなった」という意味だという説を私は大雑把に習った。それも完全な答えではないらしい。
或いは、旧来の無神論者は「神はいない」とは口にしていただろうけれども「神は死んだ」というフレーズはなかなか思いつかず、それ故にニーチェの「神は死んだ」というフレーズは注目に値した訳であって。
放送大学、本当に駄目な大学なのだろうか。そうじゃなくて私が駄目人間のような気がする。
(問)哲学の問題例の一つ、例えば「知識とは何か」について、哲学の性格づけ (1)、(2)、(3)、のそれぞれの立場からどのような答えが想像できるだろうか
――『現代哲学入門』第 I 部第 1 章「哲学について」「哲学についての複数の特徴付け」(p. 9)
(問)最善の説明をするための自然な仕方は仮説を設定して説明し、それが成功すればその仮説を正しいものとして採用することである。検査の結果から胃潰瘍を胃がんと誤って診断した場合、どのようなことが生じるか考えてみよ。
――同書同部同章 Box 1 「1. アブダクション」(p. 15)
「治療に余剰な手間と治療費がかかり、医師や検査士が患者とその関係者の怒りと不信を買うが、検査結果が胃がんならざる胃潰瘍の症例として認識され、医学の知識が増し加わる」
訳あって昨日広島県府中市上下町に往ったのだけども、上下然り東城然りああいう所で肉体労働とか事務作業とかするのも悪くないと思った。但、それが上下とか東城といった「旧市街」である必然性は余りないのだけど。
そもそも広島県でなくてもいいのである。広島県であってもそれはそれであまり差し支えないのだが。
寧ろ福塩線や藝備線や木次線みたいな鉄道が愛おしくて惜しくて、ああいうものにどうしても栄枯盛衰を覚え(昔は駅の裏にヤードがあって農協が材木とか野菜とかいった貨物を運んでいたのだろう)、どうにか復興させようと思う魂胆が自分の腹に見え隠れする。撮り鉄以上に痛い鉄おたというか鉄道厨である。
尾道道なるものができたことからして、亀井静香とかもアスファルト寄りの人士だったんだよな。まあ今の政治に求めるべくは、物流なんかより福祉だけど。
それと、昨今の大船渡のことを思うと中国地方の山林も山火事が心配。
私の HTML に関する立場は、例の歴史的仮名遣いの野嵜健秀氏による影響が大きい。まあそんな野嵜氏も Twitter なんてものに染まって HTML を余り論じなくなったけれども。
文字列を「役割」に応じてマークアップする発想、それ自体は寧ろ SGML とか HTML の当初からの方針である。例外はない訳ではないが。Tim Berners‐Lee が掲げた理想が所謂「論理マークアップ」だったか否かは議論されてもよい。
但、今の HTML(最早 HTML5 ですらないらしいが)の「small 要素は著作権表示などに用いる」なる「設定」は SGML や HTML の正統から横道にそれているどころか、日本語や中国語(特に台湾華語)などは漢字を遣うから、著作権表示とて文字が小さくなると読みにくいだけだし、私などは日本の雑誌などの目立たない所に書いてある「極端に小さい文字」そのものに恐怖のような感情を覚えるのである(この気持ち、解ってもらえるだろうか)。或いは、イラストレータさんなどは著作権に厳しい方が多いから、著作権表示を小さく記すのを望まない人も多いだろう。
そもそも small なる(名前の)タグで著作権表示を括るのは、果たして「義務」なのだろうか。そして著作権表示を「小さく」記すのも義務なのだろうか。
<small class="copyright">©渡邊朱倫 無断転載を固く禁じます</small>small.copyright {font-size: 1.5em}前記の如く、small という要素名に反して著作権表示を large に書くのは是か否か。
何らかの意味で著作権表示をマークアップしたければ copyright のような(名前の)要素を新しく造った方がよいと思う。
| ギネス認定者 | 長寿の秘訣は? |
|---|---|
| 被認定者 | お酒を飲まないことです。 |
「『正しい HTML』を書くのは検索しやすくする為」だとか「所謂『正しいHTML』は検索する上で欠陥がある」とかのたまう人がいるらしいが、私なんかは今も昔も検索エンジンなんか信用していないからそういう論法は私個人には無効なのである。「ネットサーフィン」という用語は死語になったかも知れないが、昔の私はネットサーフィン主体でウェブを閲覧していた。或いは Windows プログラムとか PC ゲームに興味があったから、Vector を中心に各所のサイトを閲覧していた。
一昔前は「正しい HTML」を書く意義は「内容は HTML、体裁はスタイルシート等に各々分離し、読者の所望に応じて多様な体裁で内容を表現する為」ということが強調されていた(「体裁」は「見栄え」という表現の方が多かったが、私は「体裁」という表現が気に入っている)。
昔の「CSS コミュニティ」だったかあの界隈の人たちは、任意のサイトに任意の「ユーザスタイルシート」を指定して、文書の体裁というか装飾を切り替えて楽しんでいる節もあった(「スタイルシート着せ替え主義」と、一時期の私は呼んでいた)。
或いは、「引用でも何でもない箇所で単なる体裁の調整を目的として blockquote タグを用いると、読み上げブラウザがそこで『以下、引用です』と発声する(可能性がある)から良くない」という議論もあった(「読み上げブラウザ論法」)。
但、今の私はそもそも文書を過度に着飾ること自体を好んでいない。一般の書籍でも、過度に装飾された本は胡散臭い、という印象がある。山陽桔梗園でも h1 に独自の方法で赤枠を与えたりしているが、これでも装飾の多い方だと思っている。
以前、WordPress について「HTML や CSS を直接編集すれば簡単なのに、サイドバーがどうこうとかいう概念を導入して煩雑にした体系」と人に批判してみせたことがある(異論は色々あろうと、今は思うが)。
で、鉄道、特にローカル線も「アスファルトにバスやトラックを走らせれば簡単なのに、閉塞だの、保線だのといった作業を必要とする分相対的に煩雑になった体系」に成り下がったのかも知れない、と今日思った(新幹線は速さなどの長所があるのだろうけど)。
14 年前の今日に限らず昔から結構地震を意識して生きている。脚立で作業している最中に地震が起きたらどうしよう、とか。
「世代」で人を判断する連中、どうにかならないのか。
どうも私は HTML の「メタデータ」という思想そのものが好きになれない。早い話がカンヴァス上に顕示してよい情報を、わざわざタグの属性にして隠蔽することが理解できない。具体的には q 要素や blockquote 要素の cite 属性などである。嘗て俗に謂われた「闇黒式引用」はそれ自体は合法だと思うが、出典自体は顕示された方がよいと思う。
もっと言えば、ハイパーリンクなる物をコンピュータ史の中でやたら劃期的な発明だと持て囃す人士がいた(今もいる?)が、私は騒ぎ立てる程の物とは思わなかった。というのが、Windows 95 の頃流通した OS やアプリケーションのヘルプも一応広義のハイパーテキストだとされるが、それで用いられるリンクを GUI のボタンの一種としか思わず、それ故にウェブに於けるハイパーテキストのリンクもボタンの一種としか思わなかったのである。
それに、ウェブに於いてはハイパーリンクに先行して URL とか URI というものが発明されているから、それをブラウザのアドレスのテキストボックスに複製してアクセスしても、少し手間が多いが、ハイパーリンクを用いるのと殆ど同じことができるのである。
ハイパーテキストってハイパーって付す程「上位」の代物か?
広島県安藝郡府中町が広島のヴァチカンなら教皇はマツダの社長? それとも府中町長?
MAZDA ってゾロアスター教の神である訳だが。
三本立ての変な夢を見た。
| 1. | 福山近郊の鉄道のレールが何故か悉く剥がされて運休になる夢。 |
|---|---|
| 2. | 母と松永に往ったが、昼飯を饂飩にするかラーメンにするか迷う夢。 |
| 3. | 駒澤大学と東京理科大学を受験して、前者には受かるが後者は「今回はご志望を廃していただきます」の如き丁寧な不合格通知を送ってくる夢。 |
それにしても駒澤往って何勉強するんだろ。まあ親に対するアンチテーゼで、キリスト教に比べりゃ仏教に好意的なこの頃だけれども。でも俺坐禅どころかマインドフルネスもできない。
あ、最近思ったんですけど、名前に元号が入っている大学に入らなくてよかったと心底思っています。「慶應」義塾大学もそうですよ。何で元号が嫌いかというと、天皇とはあまり関係なくて、元号で時代を分断する音楽番組とかが嫌いだからです。
昨日の夢の話じゃなくて現実の話だけど、「努力」が苦手だったり嫌いだったりで、物を学ぶことを本質的に楽なことだと思いこんで、手抜きをしようとしたから、東京理科大学に滑ったんだ、私。
或いはそんなに物理だの化学だのが好きだったのか、今も好きなのか否か。自然科学じゃなくて数学だが、最近、人に「二次関数いじりは大嫌いです」ってつい言ってしまった。
何というか餓鬼の頃から顔が見えないのに喋っているのが不自然でならなかった。要するにテレビ慣れしているというか。
声優の雑談も余り好きじゃないしな。
コンソールで食べ物屋のレジを再現するプログラムを書く気力がないと他の何も成し遂げられない気がしたので。
先ず十進 BASIC ってのを使ってみたけど PRINT USING 文が C の printf 函数より複雑という事実。
C++ とか Python とかをやってみたいのも山々。
日曜の昼間に再放送されてる「月曜から夜ふかし」にすら筑波大学の化学博士が出てきていつもの嫉妬。
しっかし自民党ってどうして数十年も創価学会と統一教会という教義の全く相容れない二つの宗教の肩を持てたのだろうかと、意義があるかどうか判らない感慨に耽る私。
『菜根譚』を時々読んでいる。知恵を得るというより漢文や漢文訓読に親しむつもりで。
地味な道徳書といえばそれまでだが、『菜根譚』や月めくりの徳目の如き地味な道徳すら守れない時がある。
今日のネプリーグのファイヴボンバー八百長じゃねえのか(学者と思しき人物が「芥川龍之介」も答えられない)。かくも何もかも計画的なクイズ番組も珍しい。
コンビニのネットワーク端末で鉄道の切符って発券できません? そしたらローカル線も少しは繁盛すると昔から思っている。
或いはローカル線の駅舎がコンビニ並のサーヴィスをしてくれたらとも思う。食べ物を売るとか。要は駅弁。(駅弁大学の話禁止)
でもこの前往った上下駅は田舎風情が心地よかった。
被爆八十年に便乗して「ポルノグラフィティ」とかいう名実共に下品なバンドを世界に発信してくれるな。
ついでに言うと、あれの歌う(?)「ミュージックアワー」とかいう音楽擬き、あれは音楽ではない。
ところで今年の原爆忌で梶浦由記さんが還暦になる訳だが。偶然以上の繋がりは無いか。ポ(以下略)よりは増しかとは思うけど。
大食い番組も大概だがそれより事故の瞬間がどうこうの番組が嫌というか詰まらなくて仕方ない。
ミャンマーやタイでは地震で本当に人が死んでんだぞ。引き合いに出していいのか知らないが。
宮治の車こすった話いい加減飽きた。
たい平はふなっしーでよく骨折しないよな。
何かあったのか劇場そろそろ三桁にならないのか。
大久野島の兎を殺した人が報道されていましたが、『鉄腕アトム』にクレオパトラを模したロボットが兎をチョップで殺して煙だか湯気だかを漂わせる場面があるのをどなたかご存知でしょうか。
『鉄腕アトム』って人とか動物とかがかなりえぐい死に方をする齣が多いので、当時の父兄が漫画自体を害悪視するのは仕方がない気がする。
LUNA SEA って果たして人というか赤ん坊の名前に相応なバンドか。赤ん坊が LUNA SEA 歌ったら怖いだろ。
みるくとかいちごとかも、幼稚園児のあだ名以外に遣うのはなんだか。
まあどんなにふざけた名前をつけても、どんなに立派な名前をつけても、赤ん坊は便所でもない所で排泄するのである。ある意味、モンゴルとかアイヌの、幼児に変な名前を付ける文化は、合理的な気がする(本来は邪鬼を祓ったりする目的らしいが)。
だからお役人様は現代日本にもあざな(字)の制度を設けなさいと。
産卵して自然死した鮭をアイヌ語でホッチャレと謂って、燻製には漁撈で得た鮭よりも向いているそうだが、菜食主義者というか不殺生主義者はホッチャレの燻製を食べることについてはどうお考えだろう?「人間にとって肉食は『不自然』」という主張もあるそうだが。
昔の(今もあるかも知れないけど)ヤフーの交流サーヴィスなんか、あれは SNS じゃないのか。
いやなんだか、自然科学の具体的な分野にのめり込めないんだ、私。工学の方が色々と興味がある。
フッ素っていまだに蛍石から収集してるんだろうか。PFAS の問題は人並みに興味があるんだが、フッ素にしてもリチウムにしてもレアラースにしても、本来地中に眠っている元素を無闇に地上にばらまくこと自体が人間にとって何かしら害になる予感がして怖い。
炭素だってそうだ。炭素自体は地上どころか人体にだってごまんとあるが、人間は地中の炭素を大量に掘削して、今や地球温暖化の弊害が目に見えている。
「邊と邉と辺は元々同じ漢字なんです、こういうのを異体字っていうんです、固有名詞に於いて特別に字体の相異が尊重されているんです」みたいなことを言うと案外、インテリ扱いされる。
最高裁判所の銘石には「最髙裁判所」と象嵌されているのだが、ウェブで「最髙裁判所」って書かれた記事なんてさっぱり見当たらない。
「新字体」とか「旧字体」という用語も知らず「簡単な字」「難しい字」と呼ぶ人も、結構いる。
いや、私自身が小学生用の漢字辞典を用いながら漢字ドリルに書き込みをしていたから、新字体とか旧字体っていう概念に人より慣れていたのかも知れないけど。
NHK BS のワールドニュースを観ていたら中国語の通訳者(恐らく中国人)が「データー」を連呼していた。
「米語や北京語には母音の長短の概念がない」「借用語の発音の議論をしたらきりがない」って言われればそれまでだが「『データー』と発音する人は『変な勘違い』をしている」気がするからなんだか。
「言葉に関しては誰しも何かしら勘違いして生きている」とか。
思えば朝に在京局で占いを発表してるのってフジテレビだけなんだよな。
今の時期にフジテレビに言及した時点で色々と負けのような気がする。
昔どこかで「お前は天秤座だから藝術に向いている」(大意)とか言われて藝術の道に往くのが癪な私。
「なんでも鑑定団」って番組に微妙な陰鬱感を覚えるのって私だけですか? 世間の人にとっては招き猫や高価な美術品が出てくる華やか な番組なのだろうか。
「 1 を 3 で割ると 0.333... とどこまでも割り切れないが、手では一つのものを三つに切ることができる。これが科学の限界というものだ」と細木和子は言った。一方私は「最先端の機械を用いても一つのもの(カステラとか?)を正確に三等分することはできないが、0.3 の 3 の上に点を載せれば 1/3 を正確に小数で表すことができる」ことこそ科学の限界だと思うのである。(細木和子は数学を科学扱いしていることにも注意されたい)
U+0307 とかで 3 の上に点が乗せられないのは既存のフォントの限界。
今は思っていないが、岡山時代はブルーバックスを文系の読む物だと勝手に思っていた。
「香坂鮪」という名前の作家がいるらしいが、こういう名前嫌いじゃないぞ。何故なら私も鮪が好きだからである。
「水戸鐵華」にしても「水戸納豆」と「鉄火巻」を意識した名前だし。